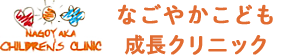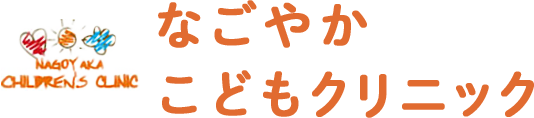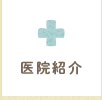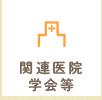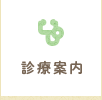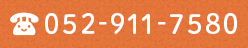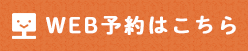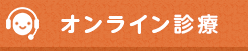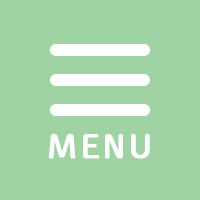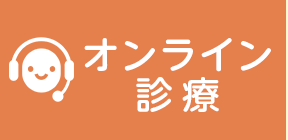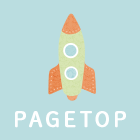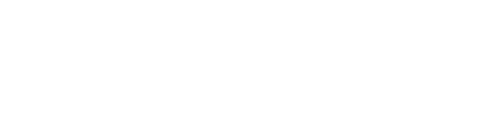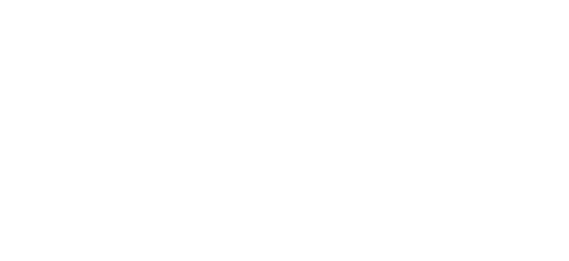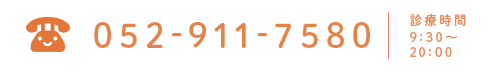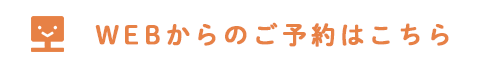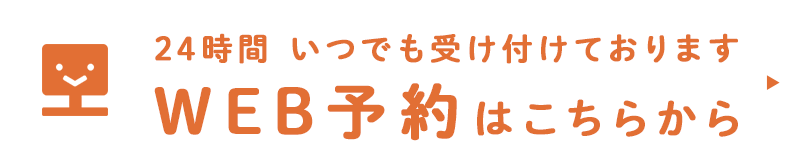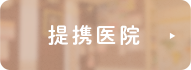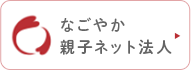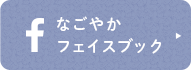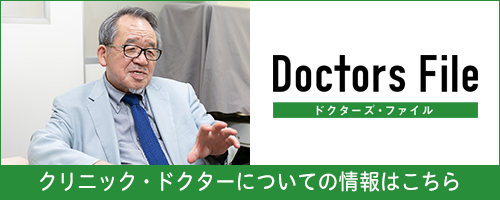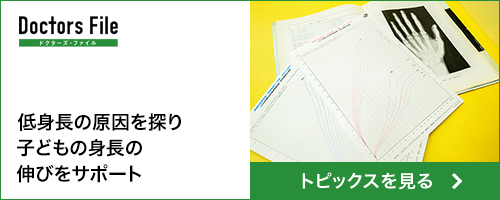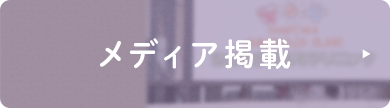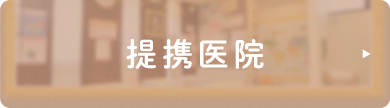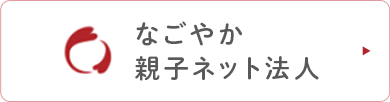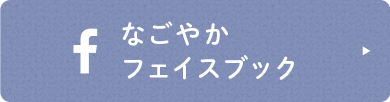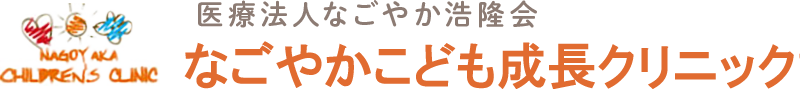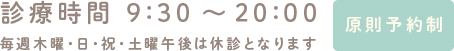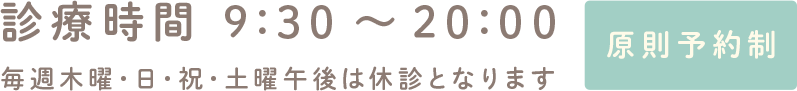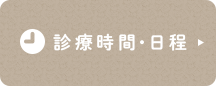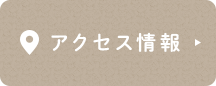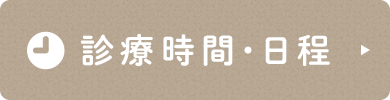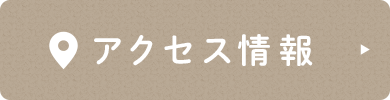2008.07.21更新
東京駒込のケーキ屋さん
昼ごろ大学3年生(東京理科大)の甥(妹の長男)と私たちが合流し、姪(妹の長女)がパテシエとして働いている駒込のケーキ屋さんに初めて行く。東京駅からJRで約30分くらいの駒込駅前の商店街にあるこの店(パテスリー)は以前にもこのブログで紹介したが「トロンコーニ」という。小さな店ながら季節ごとに創作される可愛らしいケーキが有名なようである。昭和を思わせる庶民的な商店街を通りぬけたところに「トロンコーニ」はあった。姪はこの春にはいったばかりの新人でパテシエとしての仕事ではなく、接客を行っていた。この店のオーナーの「ケーキ造りも重要だが、接客も同様あるいはそれ以上に大事」という考え方に基づいているようだ。店は10坪ほどでこじんまりとしているが(厨房は別)、出来立ての色とりどりのケーキ類が並べられている。やはり接客をしている奥様にご挨拶したあと、片隅にあるテーブル席でケーキとコーヒーなどをいただく。ケーキ好きの家内はいくつか食べようと意気込んでいたが、次から次へとお客さんがあるのであまり長居はできず、オーナーパテシエの岸上清貴氏にお礼を述べてお店をでる。岸上氏は意外?にも日本酒がお好きという姪からの情報があったので、佐渡で購入した「北雪」YK-35をお土産にお渡しする。この後甥と別れ、東海道新幹線で名古屋に戻る。この5日間は新潟、東京と楽しくまた名古屋に比べればそれほど暑さを感じない旅であった。とりわけ新潟は米、酒、魚が豊富でかつおいしく、食糧危機の叫ばれる昨今を考えると、その際には最も有利な土地ではないかと思われた。豊富な温泉もあり、ぜひまた訪れたいところである。ただこのクリニック休みの間、患者様にはご不便をおかけしたことをこの場を借りてお詫び申し上げます。
投稿者: なごやかこどもクリニック
2008.07.20更新
長岡と北越戊辰戦争
朝新潟のホテルを出て、上越新幹線で約30分で「長岡」へ到着。長岡といえば花火で有名だが、明治(幕末)の新政府(官軍)と戦ったもうひとつの戊辰戦争(北越戊辰戦争)の場であったことを知る。長岡藩は最初徳川幕府と新政府に対して中立の立場であったが、最終的には幕府側となり官軍に破れ、このときの指導者であった(家老)河井継乃助は後に激戦地となる「会津」までの転戦の最中に病死する。このため長岡城は廃城となり、現在では長岡駅近くにある長岡城址(二の丸址)がわずかに残るのみである(長岡駅付近が本丸であったようだ)。「米百俵」で有名となった「国漢学校」の跡地を市内の中心地近くに訪ねる。この話は、経済的にも苦境にあった長岡藩に送られた百俵の米を今食べるのではなく、将来の藩をになう人材を育てるために学校を作ったという風に私は理解している。つまり今現在のお腹を満たすことよりも、人材の育成(教育)が長い目でみれば重要ということだと思う。この話を元総理が間違って(故意に?)引用し、無意味な歳出削減を続けたため教育も医療も荒廃の道を歩んでしまっていることは周知のことである。
長岡市内に「吉の川」:吉の川㈱が、郊外に久保田:朝日酒造がある。久保田は千寿、万寿などがよく知られる新潟の銘酒であるが、昨年の中越地震で被害を受け一時品薄となった。現在では完全に復興し、いつでもこれらのお酒がのめることはうれしいことである。日曜日だったため蔵の見学はできなかったが、この町の歴史の一部を知ることができた。遅めの昼食を駅構内のそば屋で新潟独特の、緑色で磯の香りのする「へきそば」を食べてから新幹線で東京に向かう。この日は東京で赤坂のホテルで泊まる。
投稿者: なごやかこどもクリニック
2008.07.19更新
歴史の島、佐渡
新潟港より高速船(ジェットフォイル)に乗り約1時間で佐渡に着く。東部の港町「両津」で観光タクシーに乗り島内を回る。両津からは島の反対側(西側)にある佐渡金山を見学する。リアルな人形で当時の作業の様子がよくわかる。かなり過酷な仕事で死者も多くでたようだ。意外だったのはこの金山で細々ながら平成2年まで採掘が行われていたということだ。佐渡金山より海岸を北上すると「尖閣湾:せんかくわん」という美しい海岸がある。約2kmにわたって続く断崖絶壁はノルウェイの有名なフィヨルドに似ていることから名づけられたとのことである。ここから海岸を南に下ると美しい湾に囲まれた「真野」という町に着く。佐渡は昔から配流の地として知られているが、この中には歴史上の人物も含まれ美しくも悲しい物語が残されている。この真野には承久の乱に敗れた順徳天皇が流され22年後に46歳で崩御(1242年)される。その影響か京都の文化や言葉が残されている。「思いきや 雲の上をば余所にみて 真野の入り江に朽ち果てんとは」順徳院。順徳天皇を祭った「真野御陵」の近くに「佐渡歴史伝説館」があり順徳天皇のほか、この地に配流された日蓮聖人(1271年配流)、世阿弥(1434年配流)などの物語が人形などを使い説明されている。またこの売店では北朝鮮に拉致されたあの「ジェンキンス」さんが働いていた(せんべいを売っている)。ちなみに曽我さんの家はこの近くにあり、ひとみさんは地元の病院で働いているとのことである(ひとみさんは拉致された時は看護学校の学生)。またこの近くに「真稜」という佐渡の銘酒を醸造する「逸見酒造場」がある。突然の訪問にもかかわらず、快く蔵の案内をしていただいた。小規模な蔵ながら味わいのある酒をつくる蔵である(名古屋ではなかなか手に入らない)。「真稜」という名は「真野御陵」に由来するとのこと。「陵」は墓を表し縁起よくないため「稜」の文字を使い「真稜」となったと蔵元より説明。ここから両津港へ戻る途中「トキの森公園」(佐渡トキ保護センター)に立ち寄る。日本生まれのトキは残念ながら全滅(平成15年10月)するも、中国から贈られたトキのペアからひなが生まれ、現在では約120羽が保護飼育されている。この1部は野生に戻す計画が立てられているようである。佐渡のもう一つの銘酒として「北雪」(北雪酒造)がある。この蔵は佐渡の南の「赤泊」にあるが、今回は時間の関係で立ち寄れなかった。両津でこの「北雪」の最高峰の大吟醸酒「YK-35」買って名古屋へ送る。
半日足らずの佐渡観光のあと再び新潟市へ戻る。宿泊する市内のホテルよりそれほど遠くないところにある「丸伊」という鮨割烹店にはいる。さすがに新潟を中心とした地元の新鮮な魚がそろっている。一般には「甘えび」といわれているものが、こちらでは「南蛮えび」と呼ばれている(正式にはホッコクアマエビというそうだ)。この「南蛮えび」は佐渡の「赤泊」などでよくとれるようだ。家内と二人でしっかり呑んで食べたが値段はかなり安かった(名古屋の2/3くらいの値段)。新潟の酒と魚と寿司に大満足。明日は「長岡」に立ち寄って東京へ向かう。 
逸見酒造:真稜など

佐渡金山

佐渡尖閣湾

佐渡汽船
投稿者: なごやかこどもクリニック
2008.07.18更新
村上市と新発田市
朝「月岡温泉」より最寄のJR「豊栄(とよさか)」駅より北東へ約1時間で村上市へ。途中車窓からは一面に広がる青々とした田が延々と続き、その奥の山々とも調和し日本の原風景と感じられる。村上藩の城下町であったこの静かな町は、皇太子妃 雅子様の父方の小和田家ゆかりの地であることを知った(小和田家は代々の村上藩士)。村上市郷土資料館には祭りで引き回される山車(おしゃぎり)等とともに皇太子ご成婚の写真も展示されていた。村上駅からタクシーで約10分ほどのところに、私の好きな日本酒の一つである「〆張鶴(しめはりづる)」の宮尾酒造がある。訪ねてみると蔵の見学は行ってないとのことで、地道に酒造りに励むこの蔵らしい印象であった。新潟の酒は一般に「淡麗辛口」といわれるが、「〆張鶴」は柔らかな旨味と凛とした香りが同居するお酒である。またこの町は鮭の回遊地で種々の鮭料理があるようである。
村上市からJRで30分ほど新潟市の方面に戻ったところに新発田(しばた)市がある。ここは新発田藩の城下町で、加賀より移った溝口氏に伴って来た市島(いちじま)家が約400年前にこの地を開拓し屈指の大地主となったとのこと。今では「コシヒカリ」の一大産地となっている。この市島家の分家が醸造するのが「王紋:おうもん」である。新発田駅より歩いて数分のところにあるこの蔵を見学した(道路を挟んで向かいには諏訪神社がある)。吟醸酒としては「王紋」のほかに「夢」があり、こちらは香りもよくさわやかで女性向きかと思う。また新発田には今回訪れなかったが、すっきりとした酸味のある辛口の「菊水」の菊水酒造がある。

村上 鮭の燻製

〆張鶴(宮尾酒造)

市島酒造にて試飲: 王紋、夢、蔵など

王紋 市島酒造
投稿者: なごやかこどもクリニック
2008.07.17更新
新潟酒蔵巡りの旅
少し早めの夏休みをいただいて、家内と共に初めて新潟を訪れる。名古屋より東海道新幹線で東京を経て上越新幹線「とき」で新潟へ(上越新幹線は2階建てになっている)。名古屋を午前に出発して午後4時頃には新潟へ到着した。新潟市は人口約80万人で(日本海沿岸では初めて政令都市に指定;平成19年4月)、駅前などを歩くとビルが整然として、名古屋と似たような印象を受ける都市である。新潟市より東側の山寄りにある「月岡温泉」に泊まる。大正5年の石油の掘削時に偶然温泉に当たったのが起源のようである(白玉の湯:泉慶)。硫黄泉で黄緑色の湯のにおいはきついが、いかにも温泉らしく美肌の湯といわれている。家内はますます美人?になったようである。夕食は新鮮な魚と、新潟の地酒が各種取り揃えられている。またこの日は奇しくも一年前「中越沖地震」で多くの犠牲者のでた日である。犠牲者の方々に合掌。ともかくも新潟最初の夜を山中の静かな温泉で過ごす。 
上越新幹線 「Maxとき」:車両は2階建て

月岡温泉 ホテル泉慶にて:越後の銘酒
投稿者: なごやかこどもクリニック
2008.06.24更新
「トロンコーニ」東京駒込のケーキ屋さん
昨日東京のケーキ屋さんから、クリニックに子供むきのお菓子が送られてきました。このお店(パテイスリー)は「トロンコーニ」といい、私の姪が1年間のリヨン(フランス)でのパテイシエの勉強のあと、この春から働いています。東京でも有名な店のようで、日本のホテルやフランスでの経験のあるオーナーパテイシエ(岸上清貴氏)のもとで創作される本格的なケ-キ類が人気なようです。今回は子供むきで日もちのするものを姪が選んで送ってくれましたが、クリニックのスタッフの間では評判は上々でした。クリニックの催しの際にでも、お子さんにプレゼントできればと思っています。

かいじゅう

あじさいとカエル
投稿者: なごやかこどもクリニック
2008.06.08更新
ひだかこどもクリニック開院
6月10日に開院予定の「ひだかこどもクリニック」の内覧会に家内と共に行ってきた。日高啓量先生は名古屋大学小児科医局出身で、名古屋エキサイ会病院小児科勤務を経て今回地元で独立開業された。名大大学院生時代に私どものクリニックの土曜外来を時々手伝っていただいた先生である。知多郡東浦町の緒川(おがわ)というところにクリニックがある。金山からJRで大府まで行き、武豊線にのりかえる。三河出身(安城、岡崎)の私たちも武豊線に乗るのは多分初めてのことと思う。大府から2つ目の「緒川駅」へはあっという間に到着。おもしろかったのは2両編成の列車に1名の乗務員がいて「ワンマン列車」になっていたことだ。東海道線ではあまり見られないが、武豊線では無人駅も多くバスのように乗客が降りる時に切符を車内の乗務員が回収していた。「緒川駅」よりタクシーで「ひだかこどもクリニック」へ。
クリニックは「於大公園」の入り口の道を挟んで向かい側にある。ところで「於大」という方はあの徳川家康の奥方だった(あるいは母親)かな。後で調べておこう。いずれにしてもこのあたりは歴史のある場所のようだ。クリニックは広々として、駐車場も30台近く確保されている。名古屋市内にあり手狭で駐車場確保も難しい私共クリニックに比べて恵まれた環境である。クリニック内も明るく、子供に配慮された設計となっている。天井も高いため広々とした印象を受ける。診察室も一般と乳児健診などが別々になっていて(入り口も)理想的である。日曜日も診察(午前中)となっており患者さんには喜ばれるだろう(私よりも10歳以上若い先生なので可能と思うが)。日高先生の奥様、お母様と管理栄養士の妹さんもみえていた。1時間近く案内していただいたが、よい環境とスタッフ(小児科の経験のある看護師)に恵まれきっと成功されるだろうと思いつつタクシーで「大府駅」へ。朝から天気もよく楽しい一日であった。
於大の方 は徳川家康の母でした。緒川城(東浦町緒川)で生まれ、三河の松平広忠に嫁いで長男竹千代(のちの徳川家康)を生む。竹千代と岡崎城で暮らしたのは彼が3歳までで、於大の方は広忠と離縁し刈谷城(刈谷)で暮らす。そんな中でも家康とは音信をとり続け、今川家から自立した家康は於大を母として迎える。晩年は伝通院と号し、家康の滞在する京都伏見城で死去。於大の方は私共の故郷の三河と深く関わっていたことを今回遅ればせながら知りました。

「ひだかこどもクリニック」日高先生と共に
「ひだかこどもクリニック」知多郡東浦町大字緒川字大門一区3-2
TEL0562-82-0700、0562-57-2337
投稿者: なごやかこどもクリニック
2008.05.18更新
名古屋へもどる
弘前を昼前に出発し、青森より八戸で東北新幹線、東京より東海道新幹線と乗り継ぎ夕方7時ころ名古屋へ到着。今回の学会出席はなかなか楽しかった。内分泌の最新情報と、学生時代を過ごした懐かしい弘前そして陸奥湾の海の幸。次に弘前に来れるのは何年先か? ただこの間、外来は休診とさせてもらい患者様にはご不便をさせてしまった。明日からは通常の診療に戻る。今回の成果(カルシウム、リン代謝、甲状腺ホルモンなど)を内分泌外来に還元したいと考えている。
投稿者: なごやかこどもクリニック
2008.05.17更新
なつかしの弘前
学会2日目。朝8時より昨日のM教授が座長の一人として「遺伝子異常による甲状腺疾患」というシンポジウムが開催された。昨日遅くまで呑んでいた私も何とかギリギリで間に合う。O先生が「SITSHをきたす遺伝子異常」について、P教授が「Pendred syndrome」について講演される(またもや専門的用語ですみません)。P教授はドイツ人だが非常にきれいでわかりやすい英語だ。2題ともに最新の研究の情報が満載されている。昼のランチョンセミナー(昼食をとりながら講演を聴く)では「増田恵子さんと語る:甲状腺機能亢進症との付き合い方」に参加。「増田恵子」といえばあのピンクレデイの「ケイちゃん」で、私たちの世代には懐かしい人である(といっても彼女はまだ現役で活躍中だが)。会場の前の方の席がとれたので、かなり近くから彼女を見ることができた! 昔よりも年はとっているものの(失礼)、華奢で美しい人である。彼女がバセドウ病を発症して、10年以上内服治療(メルカゾール)をしていることを初めて知った。何回も再発(再燃)を繰り返しながらも、仕事にも治療にも前向きに取り組んでいるのが印象的であった。それにしても彼女の主治医は誰だろうか?診察とはいえ、おそらく月に一回くらいは彼女と会うことになるのだから羨ましい限りだ。 午後の会長講演を聴いた後、弘前(ひろさき)へ移動。青森から列車で約30分で弘前に着く。弘前駅は立派なビルに変わり昔の面影はほとんどない。昔は小さな駅舎とその周りにリンゴ箱を置いたお土産店がいくつかあって、いかにも「みちのく」といった風情であったのが懐かしい。それにしてもこのところ新たに建て替えられる駅が立派ではあるが、その地方独特の個性がなくなってしまったのはなぜだろうか(松本駅も往年の風情がなくなってしまった)。駅のすぐ近くにあるホテルにチェックインして、タクシーで弘前城へ。さすがにこの城は約30年前とほとんど変わりない。100年経っても200年経っても変わらないものがあるというのは本当にいいものだ。学生時代この城内を一人で歩いたり、桜の季節は仲間と花見をしたことなど懐かしく思い出される(弘前の桜はその質と量において日本一と思う)。この城を中心に数多くの寺が散在し、伝統工芸など昔からの津軽藩以来の文化が引き継がれている。弘前のidentityは弘前城といっていいだろう。弘前城がなければ弘前はただのリンゴの町になってしまう。

夕方まで時間があったので弘前大学のキャンパス(医学部ではなく教養課程のある本学)に行ってみた。ここへは昭和54年の卒業以来29年ぶりに来た。門構えが立派になり、建物も増えていたがあの頃と大きな変わりはなさそう。この大学はなぜか正門の向かいに2,3軒の居酒屋があり、友人とちょくちょく通ったものだ(もちろん20歳を過ぎてからですよ)。そのうちの一軒はおばあちゃんが一人でやっていた店だが、建物はまだ残っていた。隣の店で聞くとこの数年は開いていないとのこと(あのおばあちゃんは亡くなったのだろうか、合掌)。ここから歩いて10分くらいの富士見町というところで5年間下宿生活をした。「葛西下宿」のおばさんが亡くなってもう長くなるので、すでに閉めているかと思いつつ昔の記憶をたどり歩いたところこの下宿を発見! しかも玄関の脇には下宿人のものと思われる自転車が数台置かれ、今も下宿としてやっているようだ。玄関を開けて声をかけても誰もいないようだ。それにしても、このあたりはまだ安全な地区のようだ。写真だけ撮って弘前の中心部に出る。
「土手町」にはデパートなどがあり買い物客などが多く、隣の「鍛治町」は飲食街となっている。規模は小さいが名古屋で言うと「栄」と「錦」といった感じか。「鍛治町」を少し歩くとかつての記憶がよみがえってきた。新しい店も多いが、昔ながらの店(和食系)もちらほら。その中で、昔時々行った焼き鳥屋があったので飛び込む。店内は以前とほとんど変わらず、黙々と鳥を焼く親父さんもあの時と同一人物と思われる。約30年前にタイムスリップしたようで、酒がおいしい(これはいつものことか)。この店は院長おすすめにいれておこう。弘前に行かれる予定で日本酒の好きな方は、
 とり畔(はん):弘前市鍛治町丸み小路TEL0172-35-1237へ一度お運びを。
とり畔(はん):弘前市鍛治町丸み小路TEL0172-35-1237へ一度お運びを。
投稿者: なごやかこどもクリニック
2008.05.16更新
とげ栗蟹
今日は学会初日。学会場の「ホテル青森」
ではいくつかの口演や教育講演などが同時進行している。この中から自分の関係する、あるいは興味あるテーマを選んで聴きに行くわけだが、私はこの日は「副甲状腺機能低下症の病因と病態」と「カルシウム、リン代謝異常症の新知見」を聴いた。クリニックで診療をしているだけだと最新の知識を得ることが難しいが、レベルの高い学会に参加するとその分野での最先端の問題を捉えることができる(専門的な話題ですみません)。
今日も夜は寿司。日本酒好きの私には寿司が最も合うようだ。青森一とも言われる「天ふじ」という寿司屋に、名古屋からのM教授、H助教授そしてドイツからのP教授とともに行く。ドイツ人の教授というといかめしそうな人物を思い浮かべそうだが、私と同じ小児科医であるP教授は見かけも若くみえることもあって、気さくな好青年といった感じだ。評判のとおりネタも新鮮で、大将の腕もピカ一であった。大間とは別の海域でとれたというマグロも極上の味。この次期にこの地方でのみとれる「とげ栗蟹」を初めて食べる。確かに甲羅が「いが栗」のような形をしている。

小ぶりだが身がしまって、こくのある味わいで卵もかなりつまっている。お酒は青森を代表する「田酒」。香り高く、すっきりした「田酒」は私の好きなお酒の一つで名古屋でも手にはいるが、最高ランクの「田酒」で大将が自分用に取り寄せているものを呑ませてもらった。「とげ栗蟹」と「田酒」、これぞ青森の味といったところか。この寿司屋で偶然仙台のH先生ご夫妻と同じカウンターになる。H先生は成長ホルモンの基礎、臨床で東北地方での草分け的存在である。そんなこんなで話もはずみ、楽しい夜だった。ところでこの店は味も一流だが値段も一流であった(東京の一流どころとあまり変わらない)。この店はあのトヨタの豊田章一郎さんが時々みえると聞くと、この値段も何となく納得。いつもは遅くまで呑むのだが、明日は朝一番でM教授が座長でP教授と昨日のO先生がシンポジストとして講演されるので早めに切り上げる(といってもホテルに戻ったのはPM10時を過ぎていたが)。

「天ふじ」の大将
投稿者: なごやかこどもクリニック